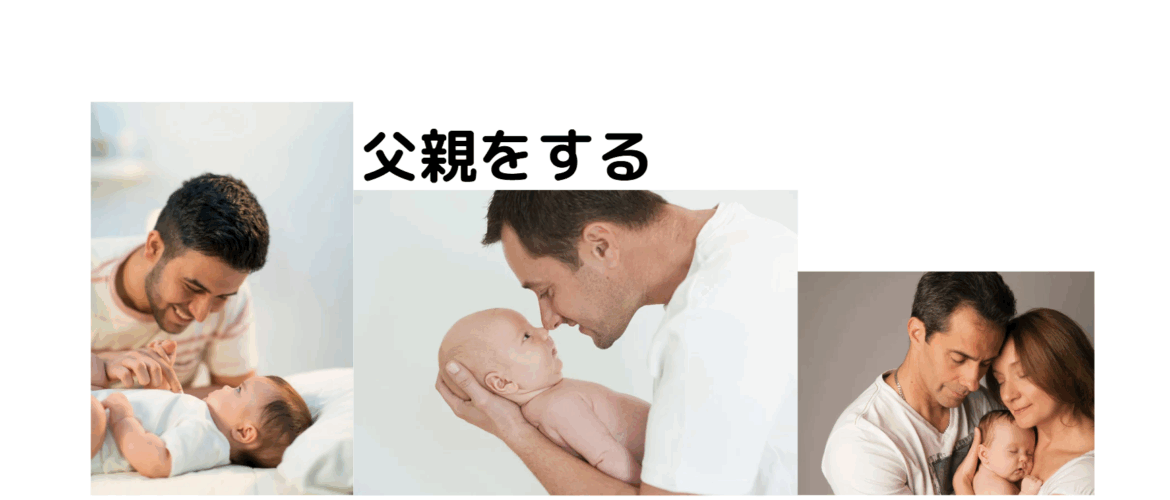ケーススタディ
父の日のメッセージ
これから父になる人へ 子育て中のパパへ 悲しい離婚にならないために
結婚して子どもが生まれて、しあわせなはずなのに、子育てをめぐって夫婦ゲンカがはじまる。実はよくあることなのです!
離婚率が高くなる時期は赤ちゃんが生まれて、ゼロ歳~3歳くらいまでが高くなっています。それは、共働きか専業主婦かに限らず、どちらのケースでもそうなんです。働いていて忙しいからではないのです!ここポイント。
つまり、ひとりで家事育児をやることになっているかどうか?なのです。ここです!ここを解消することで平和で穏やかな家庭が形成されていくでしょう。それにはパートナーの存在が欠かせません。どちらかがメインではなく、二人がメインです。二人がどちらも主体的に動くことです。二人が助け合い協力し合うことです。
そうでないと『なんで私ばっかり』『おればっかり』という不満が出ます。不満は弱いところ(子ども)に八つ当たりとなって顕れます。怖いことです。子どもの人格形成にもっともだいじな時期ゼロ歳~9歳、この時期に夫婦の争いを子に見せ、不満のはけ口にしたのでは良好な人格は形成されにくくなります。
人間の子どもを育てるということはどういうことなのか?改めて考えてみましょう。
もともとは部落のような集落の集団生活の中で子育てはみんなの手でおこなわれていました。21世紀の今でもアフリカの奥地では見られることですが人間は進化しました。文明が進み私たち人間の暮らしは見る見る変わっていきました。
日本でも昭和の戦後(1945年)から数年経ち、高度経済成長に伴い、都市部を中心に産業構造が変わり生活スタイルも変わってきました。また経済性と利便性を求めて地方から都市部へ移り住む人、学業を求めて来る若者たちもどんどん増えて「核家族化」が進みました。この頃から家事・育児を夫婦2人が担い手となり、仕事のほかに負担を感じることが増えてきました。※注:決して核家族が悪いわけではありません。むしろ明治時代からの「家制度」の名残から解放された点はすごく良かった点だと思います。
さらに、現代では女性の社会進出も広がり女性がひとりの人間として自分らしく活躍できるチャンスが増えました。これは素晴らしいことです。今まで政治も経済も男性中心の社会だったため、政治も経済も決め事自体が男性都合でした。人間として非常にバランスの欠いた社会になっていました。女性は男性の付属品のように扱われたり、優秀な女性もたくさんいるのに意見を言えば潰されてきました。政治経済に女性の視点がないことは世界的に視て決して得策ではありませんでした。ここが社会課題となりました。そして男女共同参画社会へと意識は変わってきました。
そこで現代からの未来は
大家族から社会家族へ
社会全体で「子を育てる」という認識が必須となりました。私の考えは「子どもはやがておとなになり、社会をつくる構成する社会の子」として捉えることがベストだと思うのです。企業も、子どものいない家庭も、独身の人も、教育現場も、みんなが「社会の子」として育てることができたらどんなに素晴らしいことかと思います。みんなが「わたしたちの子」として捉えれば、「うちの子」「よその子」という無用な競争も見栄も体裁も偏見もなくなり、競争心から生まれるいじめや嫌がらせも減るのではないかと考えます。
みんなの手を借りて育てていく。現在でも既にベビーシッター、保育園、社内保育、幼稚園、学童保育、塾や習い事の送迎、また家事も整理収納の専門家、献立から調理までやってくれる家事ペルパーさん、多くの人の手を借りて家事育児が賄われているケースもあります。
とは言っても、家庭の中では夫婦。直接子どもにかかわる重要性はもっとも大切なことです。
なんといっても子育ては生涯の中で最も「重要な大プロジェクト」ですから、父親母親、養育者の人たちは、たっぷりの愛情で子どもに安心を与える存在であってほしいものだと思います。
そこでここからは父親の存在とはなんなのか?
夫であり、父親となった男性の役割はとてもだいじで大切な役割です。
「人間にとって父親になるとはどういうことなのか?」
について、私の尊敬する柏木惠子先生のご著書「父親になる、父親をする」~家族心理学の視点から~を参考にしていっしょに考えてみたいと思い動画をつくりました。
現代では「イクメン」の言葉も定着しつつあり、ベビーカーを押すパパ、前抱っこで買い物をするパパ、保育園の送迎をするパパ、よく見かけるようになりました。それでも、育児休業が取りづらい、「育児があるので早くかえりたい」と言いづらい、まだまだ日本では企業によって大きな格差があります。
パパの育児時間が少ないと、夫婦関係はもちろんのこと、いろいろな弊害が生まれます。パパの育児が可能な社会にするためにはどうしたらいいでしょう?
子どもがいるいないに関わらず、世の中全体で、みんなで子育てしていこう!という共通認識が必要です。
だって、子どもは社会の子、やがておとなになって社会を支えてくれるのです。人類の持続可能な社会を築く大切な一員です。もう「家制度」が廃止になって77年経っています。もう子どもは「家系」をつなぐためのものではなく、社会全体をつないでいく、人類をつないでいく大切な存在なのです!
動画はこちらから☟
#家族 #心理 #父親 #カウンセリング #イクメン #コミュニケーション #夫婦 #夫婦問題 #親子 #ファザー